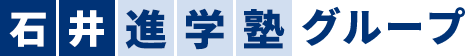秋は、受験生にとっての新しいスタート地点です。松阪市の学び場から、慶應義塾大学卒の石井宏明が30年以上の指導経験を活かし、秋に取り組むべき3つのポイントを、やさしく丁寧にお伝えします。個別指導と集中できる環境づくりを軸に、心と学力の両方を育てる道しるべです。保護者の方にも、具体的なサポートのヒントをお届けします。
ポイント1 秋に最優先で取り組むべき勉強の内容と効果的な秋の学習計画
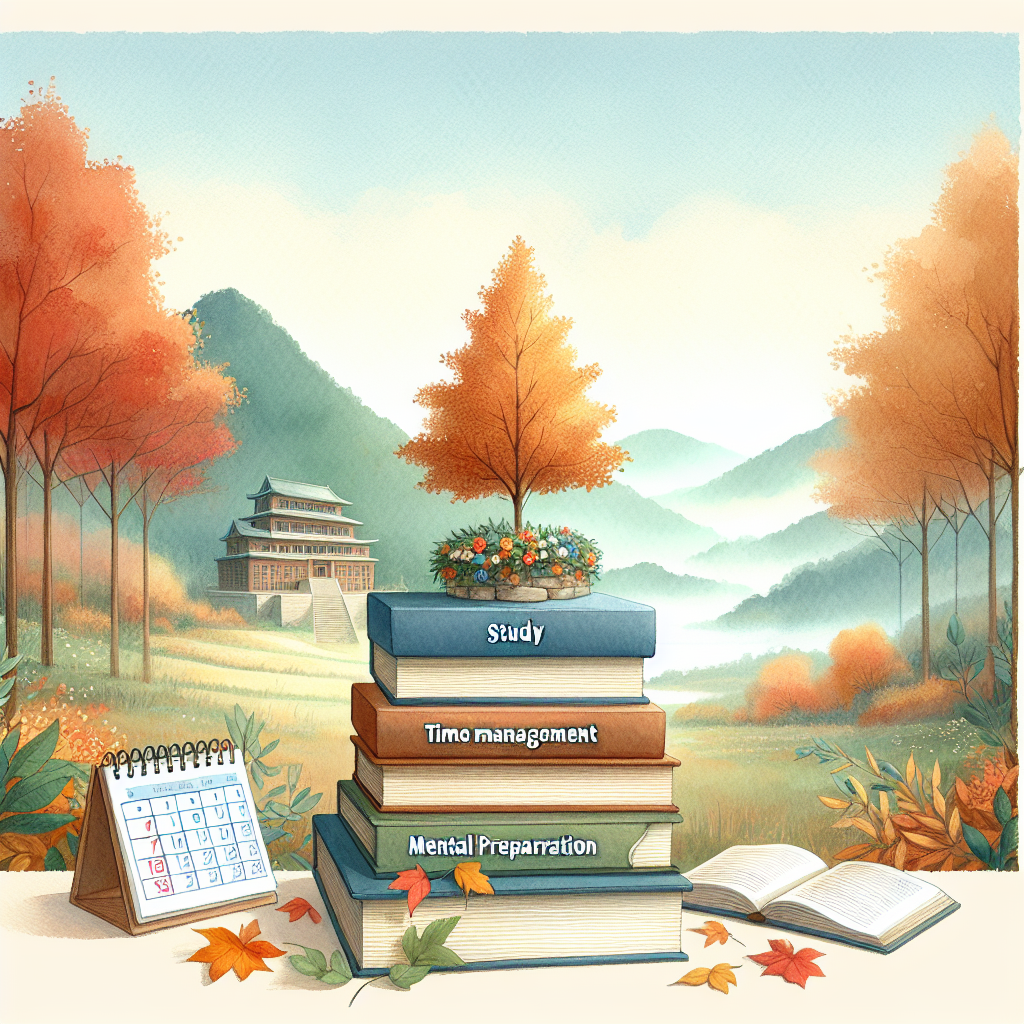
秋は「基礎の完成」と「過去問の土台作り」を同時に進める時期です。夏の総復習の成果を確実に自分の力に変える場です。
具体的な内容と計画の作り方
- 毎日10〜20分の基礎復習を習慣化。科目ごとの基本問題→応用問題の流れを作る。
- 苦手科目は「穴埋めリスト」を作り、弱点を朝の短時間で埋める。
- 英語は長文の読み慣れと語彙強化。毎日1題の長文読解と、出てくる語の意味をノートに。
- 数学は公式・定理の定着。1日1問の反復演習で解法の型を身につける。
- 理科・社会は重要論点の整理と用語の暗記を、地図・年表・因果関係で結びつける。
- 定期テスト対策と推薦・AO対策を意識。得点につながる科目は「点になる学習」に落とす。
秋の学習計画のコツ
- 志望校の出題傾向を小さく分析。過去問は「3年分」を目安に手を動かす。
- 週の学習量を「負荷=維持可能な量」に設定。休憩と睡眠を確保する。
- 進捗は週次で振り返る。うまくいかない日は原因を分析して次週へ活かす。
保護者の方へ。お子さんのペースを尊重しつつ、睡眠時間と朝のルーティンを整えるだけで、学習効率は大きく上がります。小さな変化を見逃さず、一緒に前進しましょう。
ポイント2 模試・過去問の活用法と秋の復習ペース・スケジュールの決め方
模試と過去問は、秋の大切な地図です。自分の現在地と志望校の傾向を数字で把握するチャンスです。
活用の基本
- 模試は「現状把握」と「傾向把握」のセットで使う。
- 過去問は「志望校の直近3年分」を中心に、解く・分析する・再現する流れを守る。
- 復習ペースは、1問に対して「気づき・解法・ミスの原因」の3点を明確化。次回に同じミスを繰り返さないことを最優先。
秋のスケジュール例
- 週1回: 模試の復習を徹底。苦手分野を可視化。
- 週2〜3日: 過去問の解答演習。科目ごとに目標解答数を設定。
- 毎日: 復習のルーティンを組み込み、1日の終わりに「今日はここまで」と振り返る。
実践のヒント。解くときは“時間配分”を必ず意識します。解答プロセスだけでなく、所要時間をノートに記録する習慣をつけると、実戦力が上がります。
ポイント3 志望校の出題傾向を秋に把握し、科目別にいつまでにどの範囲を仕上げるべきか
志望校の出題傾向を秋に掴むには、情報を集めて分析する習慣を作ります。学校説明会、模試の分析ノート、塾の分析資料が頼りです。
科目別のロードマップの例
- 国語: 漢字・語彙を固め、現代文は文章構造と要点の把握を速くする。9月中旬〜11月末までに現代文の長文演習を20題程度増やす。
- 英語: 長文読解と英文法・語彙の総合力。9〜11月で長文30題、英作文の練習を始める。
- 数学: 基礎の定着→応用の積み上げ。9〜11月で過去問に対応できる解法パターンを20題以上身につける。
- 理科: 重要論点の整理と暗記を、現象の因果で結ぶ。12月は過去問中心で総仕上げ。
- 社会: 年表・用語・地理・政治経済の整理。傾向に合わせて、11月までに過去問の対応力を高める。
秋は、情報をとことん集めて分析する時期です。志望校の出題傾向を“自分の手の内”にすることがゴールです。私たちの3ヶ月以内に結果が出る指導は、個別指導と集中できる環境づくりを軸に、心のケアも大切にします。保護者の方と一緒に、無理のない計画で着実に進めていきます。
秋の終わりには、あなたの努力が小さな自信へと変わっているはずです。焦らず、しかし確実に。松阪市の皆さんとともに、志望校合格の最短ルートを描きましょう。石井宏明は、あなたの未来を一緒に支える伴走者でありたいと思っています。